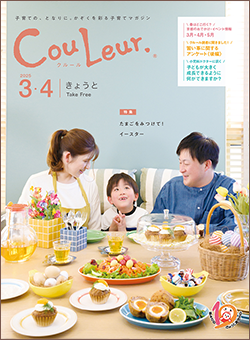みなさんのお子さんが初めて話した意味のあることばはなんだったでしょうか。
個人差はありますが、子どもは1歳を過ぎたころ、意味のあることばを話すようになります。その子にとってはじめて話した意味を持つことばを、専門用語で「初語(しょご)」といいます。
私が教えている大学の講義で、学生たちの初語がなんだったかを保育者に聞いてくる宿題を出すと、大半が「まんま(ご飯の意味)」「ママ」と答えます。海外での調査でも母親を指す言葉が多いようです。
そこで、我が家では長男誕生時にある実験をしました。家庭で、母親のことを「お母さん」と呼び、「ママ」ということばを一切聞かせずに育てたのです。
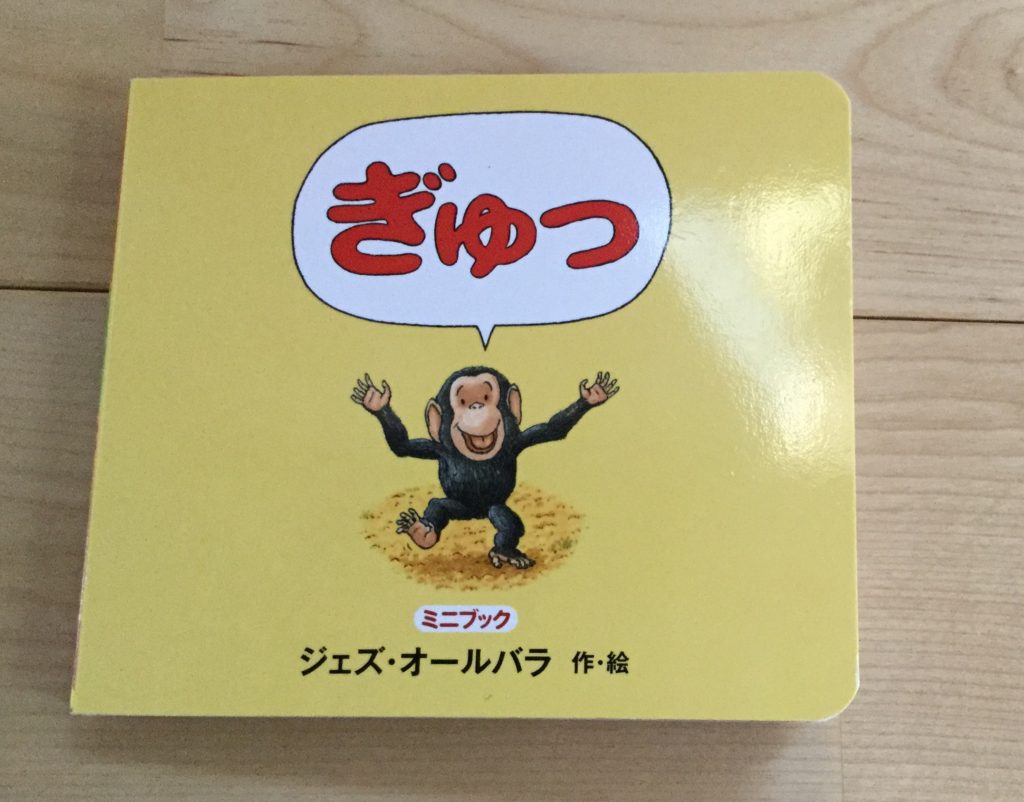
息子のお気に入りの絵本。「ママ」という言葉が出てきますが「お母さん」と読み替えて聞かせました。
『ぎゅっ』ジェズ・オールバラ 作・絵 徳間書店
ところが、息子は1歳になる少し前から、母親の姿が見えなくなれば「ママーー」と探し回り、お腹が空いては母親を見て「ママー、ママー」と泣くのです。我が家では「ママ」だけでなく、「まんま」という幼児語も一切使用していないので、おそらくこれは意味を持たない「音」でしょう。唇を使って発音できる“m”の音は、赤ちゃんにとって発音しやすい音なので、よく発していたのだと思います。
その後、1歳4ヶ月を迎える日、ついに初語が出現しました。手にとうもろこしを持って、こちらに差し出しながら「どうじょ」と微笑む息子。夫と2人で思わず「喋った!!!」と叫びました。
ところで、初語は1歳前後で出現すると言われていますが、初語が出たらどんどん喋り始めるわけではありません。しばらくは潜伏期があり、半年ほどすると突然たくさんのことばを話し始めると言われています。ただ、話せないからと言って理解していないわけではありません。
この時期の赤ちゃんは、ことばの産出と理解が別々に発達しており、聞こえてくることばから単語を切り出すことで、たくさんの音の並びを記憶に溜め込んでいるのです。
実は、赤ちゃんは一度聞いたことを数週間覚えていることが可能で、再び同じ音の並びが聞こえると、それを切り出して単語として覚えていくと言われています。
ただし、2歳以前の子どもの場合、DVDやTVなどからことばを学ぶことは少なく、ことばを通した人とのやりとりや触れ合いが非常に重要であることが分かっています。みなさんも隙間時間でも構いませんので、絵本や手遊び歌などを通して、お子さんとかかわる時間をとってみてくださいね。
ーーーーーーーーーー
小口悠紀子さん

専門は第二言語習得研究者。広島市立大学国際学部講師 。マレーシア、韓国、トルコ、フィリピンなどで日本語を教えた経験を経て、現在は大学で留学生への日本語指導や日本語教員養成に携わる。主な著書に『超基礎日本語教育』(くろしお出版)、『日本語教育へのいざない ―「日本語を教える」ということ―』(凡人社)。