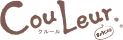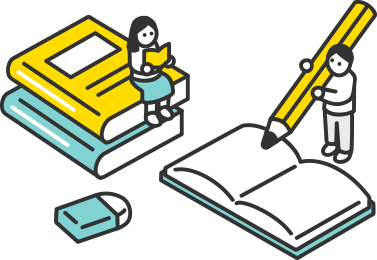
4年生
10歳での決意表明
「立志式」
小中高大の一貫教育を行っている立命館学園では、小学校から高校までの12年間を4年ごとの3つのステージに分けています。ファーストステージの締めくくりとなる4年生の3月には、10歳の自分の将来の夢や目標など自分なりの生き方を決意表明する「立志式」が行われます。当日は、子どもたちが保護者や教員、そして仲間に自分たちの思いを届けます。
自分の思いを届けるためには、自分の思いを知る必要があります。自分がどのように生きたいのかを知るためには、たくさんの人の生き方に触れる必要があります。昨年度は、立志式に向けて、当時の立命館小学校の校長だった堀江未来先生(立命館大学教授)から、海外を飛び回りながら自分の人生をつくっているお話を聞いたり、社会科の授業では地域の発展に尽くした人々の学習から、どのような思いで地域を発展させたのかを学んだりしました。
そして、さらに多くの人から、それもできるだけ身近な大人から学んでほしいという思いから「保護者サポータ―」の制度を活用することにしました。

立志式に向けた事前学習
保護者の生き方を
子どもたちに語る
「子どもたちの前でご自身の生き方について語ってくれませんか?」「ご自身のお仕事のことなどを子どもたちに紹介してみませんか?」と保護者サポーターの方を募集させていただきました。「どれくらいの人が参加してくださるのかな」「どんな方が集まってくださるのだろう」。このような募集をすること自体初めてでしたので、どのような結果になるのか、ドキドキしながら保護者の方の反応を待っていました。

そして、8名の保護者の方々が名乗りを上げてくださいました。当日はその保護者の方々が、それぞれの生き方を語ってくださいました。職業のことはもちろん、なぜそのような仕事をすることになったのか、さらには今でも大切にしていることなど、保護者の方が等身大で語ってくださっていた姿が印象的でした。
この「保護者サポーター」のみなさんの声は、子どもたちの心の中まで届き、何名もの子どもたちが、立志式の本番で保護者の方の生き方から得た学びをもとに、自分の決意表明をしていました。このときの子どもたちの姿を見て、保護者サポーターのみなさんに協力していただき、本当によかったなと思いました。

保護者の方の話を真剣に聞き入る
3年生
「おうちの人と一緒に!!」
まち探検の学習
3年生の1学期、「まち探検」という学習があります。その名の通り、自分たちの学校の近くのまちに出かけて学習を行う校外学習で、学校のまわりをぐるっと一周して気がついたことや疑問に思うことを出し合っていきます。
まち探検に出かけた後の授業参観で、探検のふり返りを行いました。参観では、子どもたちが次々に発表をして話し合っていくなかで、「あれ?ここはどうなっていたかな?」「そう言われるとどうだったっけ?」と、それぞれの気づきから、子どもたちは「二度目のまち探検に出かけて、さらに調べたい」という意欲を高めている様子でした。
「ただ、これだけ多くの疑問をまち探検で調べるためには、グループを分けて学習しないと難しいなぁ」「でも先生たちの人数は限られているし、どうしたらいいだろうか…」と、私が悩んでいるときに、ある子が手をあげて発言しました。
「先生、ここにいるおうちの人に手伝ってもらったらいいんじゃない?」
子どもたちの声から保護者サポーターにつながる瞬間でした。「それいいね!」と、後日、保護者サポーターとしてまち探検に一緒に行ってくださる方を募ると、すぐにたくさんの保護者の方が集まってくださいました。
二度目のまち探検は、子どもたちと一緒に活動に参加していただく学習となるので、保護者の方には、「子どもたちに質問を投げかけてほしい」ということ、さらには「聞かれたことがあれば、わかる範囲で答えてあげてほしい」ということをお伝えしました。また、子どもたちがまち探検で発見したポイントについて写真を撮影していただくこともお願いしました。このとき撮られた写真は、その後の子どもたちの学習で活用されていくこととなります。
子どもたちの学びの輪の中に入っていただいたことによって、保護者の方にとっても「子どもたちの見る視点が新たな気づきになりました」「子どもたちはこのようなことを考えているのですね」と、授業参観だけでは得ることのできない新たな発見があったようです。

5年生
子どもたちと
「平和について話し合う」
5年生は宿泊体験学習で広島を訪問します。平和について事前学習を行い、広島から帰った後にも、考えを深めていくために事後学習を行います。戦争や平和について見学や講話を通して知ることはもちろんですが、この期間には、だれもが重要だと思っている平和を捉え直していきます。そもそも私たちにとっての平和とはいったい何か、そして私たちは平和をつくるために何ができるのか、ということです。これについては、私たち教員も子どもたちと議論する中で、いつも子どもたちの視点や発想に驚かされます。大人が捉え、理解している平和とはまったく異なる視点、価値観で平和を考えていることが見え、興味深いのです。
宿泊体験学習の成果を発表する機会をつくるにあたって、2023年度からは、授業参観の場を活用して保護者の方を交えた「平和サミット」を開催しています。発表というと、大勢の前で子どもたちが一方的に話をする場をイメージされるかもしれませんが、今回は児童と保護者混成の班編成にして、班の中で対話する形にしました。自分の親を目の前にして、平和についての考えを述べる。家庭では普段あまり話題にしない平和について、真面目に我が子が語っている。自然と保護者も含めた議論が熱を帯びていきます。その語り合う姿は、私たち教員にとっても感動的な光景でした。

保護者を交えた平和サミットの様子
児童、教員に保護者が
加わり三位一体で
教育パワーをアップ
「保護者サポーター」の呼びかけは昨年度から始めたばかりです。しかしながら、本校の保護者のみなさんは常日頃から立命館の教育に強い関心をお持ちで、参観日や行事の日の来校率はとても高いです。そこをもう一歩、より深く学校と関わっていただいて、より濃く学校とつながっていただけたら、相乗効果で有意義な学びの場となり、子どもたちにとっては教えてくれる大人が増え、教師にとっては、先生という職業の範囲外の視点から学ぶことが多くなります。そして保護者のみなさん自身にとっても、子どもの意外な面を発見したり、自分自身を振り返ったりと、得難い機会になっていると思います。「保護者サポーター」制度を発展させて、子ども、保護者、教職員がともに成長できる、そんな学校を一緒につくっていきたいですね。

子どもと大人が、
学び合い、育て合う。立命館小学校は、
“ラーニング・コミュニティ”へ