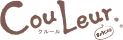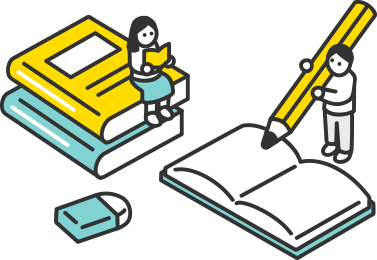
不安も吹き飛ぶ
頼れる6年生の存在
創立以来異学年交流を大切にしている立命館小学校では、1年生から6年生が縦割りで活動する「ハウス活動」を活発に行っています。それに加えて、1年生と6年生がひとりずつ「ペア」になり、1年生が2年生になるまでの一年間、さまざまな交流の機会を設けて学びの場をつくっています。6年生はそれまでの学校生活で異学年交流をたくさん経験していることもあって、たいへん面倒見がよいですね。本当の妹、弟のように接しています。1年生のほうは、新しく始まった学校という空間での生活に、頼れるお姉さんお兄さんがいてくれることで不安も吹き飛びます。
1学期の初めに顔を合わせ、自己紹介の際には、自分の名前とメッセージを書いた自作の名刺を交換するんです。少し緊張していた1年生と6年生も、この瞬間笑顔になり、「ペア」の顔と名前を覚えます。

まるで本当の家族のように
その後、1年生の給食の配膳と片づけを6年生が手伝いに行ったり、合同授業でダンスをしたり、さまざまな形で交流します。さらに、6年生は1学期に宿泊学習がありますが、旅先から自分のペアの1年生に宛てて葉書を送るんです。これは、受け取った1年生が大喜びするのはもちろんですが、送るほうも、ちゃんと届くかな、読んでくれるかな、喜んでもらえるかな……とドキドキして投函していますから、宿泊学習から帰って登校した時に1年生に再会するのがとても楽しみなんですよ。このように、学校生活のいろいろな場面で交流を重ね、互いをよく知るようになります。とくに6年生は、自分のペアの1年生について、得意なことや苦手なこと、好き嫌いなどを少しずつ把握していきます。まるで、本当の家族の一員のように、大事な存在として関わろうとする姿が見られます。

給食のよそい方や配膳を6年生から学びます

6年生に教わると1年生の目もキラキラします!
「時計」
生活に直結する算数
このような関係が築けたところで、学習面での交流も行っています。算数科では、2学期と3学期に6年生が1年生の学習を手伝います。最初は「時計」の学習です。時計の模型を使い、長針と短針の動きをおさらいし、何時何分を指しているか、ここから15分経過したら針はどこを指すか、といった基本的なことを教え、確かめていきます。現在はデジタル時計が当たり前ですから、アナログ時計をあまり見たことがない1年生もいます。また、チャイムが鳴らない立命館小学校では自分で時計を見て動く場面が多くあります。そんな1年生に対して、6年生は、どう説明すればしっかりわかってもらえるか、さまざまな工夫をしてペア学習に臨みます。アナログ時計で学ぶことは現在時刻の見方だけではないんです。角度を知ること、十二進法の概念を覚えること、時間を分量として測ること、など、このあと続く数学的な学びにつながる要素が多々あります。そしてそれらは、やはり算数や数学の枠を超えて、生活に直結していきます。
6年生にとっては教える工夫をするなかでこういったことをあらためて認識したり、発見したりするので、自らの理解が進み、学びが深まります。

工夫を凝らしどうすれば1年生に伝わるかを考えます
中学・高校への
スモールステップ
どの教科にも言えますが、とくに算数という教科は無理のない学習の積み重ねが大切です。単元が変わると難易度がいきなり上がる、といった壁ができないよう、スモールステップで進めるように授業も工夫しています。実は、私は算数の苦手な子どもだったのですが、中学で教わった先生が素晴しくて、数学が面白くなったのです。みんなが算数・数学を好きになってくれるように、さまざまな取り組みにチャレンジしたいと思っています。
例えば立命館高校の生徒が来校し算数を教える「学習サポート」という取り組みがあるのですが、ここでは今まで1年生に「教える側」だった6年生が「教わる側」になります。中学進学を目前にした6年生たちは「なんだか難しそう」という先入観だけで算数・数学に苦手意識や不安をもってしまいがちですが、身近な先輩が寄り添っていっしょに問題を解いたり、質問に答えてくれたり助言をしてくれることは、心に大きく響いているようです。中1ギャップの解消にもつながっていると思います。

学習サポートの様子。「教える側」から「教わる側」に
共に成長する
「異年齢共修」
このように「教える側」「教わる側」を経験したのち、3学期には再び1年生に「教える側」を経験します。「定規」の学習なのですが、これは「時計」よりも教える側の自由度が高い、言い換えれば、より創意工夫が必要になります。オリジナル教材をつくって、定規の使い方を教えます。線を引いて絵を描いたり、長さを測ったりして遊びながら、定規を上手に使えるように、使うのが楽しくなるように、6年生なりに工夫を凝らして教えています。そうやってお兄さんお姉さんに一生懸命教えてもらったことは、1年生の心の中に幸せな記憶として残ります。それが、1年生が成長して逆に「教える側」になったときに生かされる。異年齢で教え、教わることでお互い成長できる「異年齢共修」で生まれる学びの循環がこれからも続いていってほしいと思います。